進路主幹 田中 秀樹
私は生来の弱視で、小学校1年から4年まで盲学校小学部に通っておりました。写真は小学校時代の授業風景で、担任の先生が撮ってくださったものです。弱視者は、このように書物を眼前数センチの至近距離に保持して、それを舐めるような姿勢で読書をするのです。一方で、このことが子供同士の心ないからかいの部分であったりし、悔しさを覚えたこともありました。
私たちは文書を読むにあたって、一文字ごとの字面を追って記憶と照合しているのではなく、単語単位あるいは短い文節単位でひとかたまりの文字パターン(画像)として認識しています。この能力獲得は、脳が成熟途上にある小学校時代まで旺盛で、そのため我が国の国語教育はこの時期に母国語(特に漢字)の文字パターン認識を獲得させることに注力しています。
文字を見続ける目、それを発声していく口、言葉にした声を聞く耳、 …… 小学部の授業は目・口・耳を総動員して、これから視覚障害者として生きていくためのトレーニングの時間でした。音読はたどたどしく時間がかかり、読み違いは直ちに先生から指摘をされて、自分が情けなくなりベソをかいていた覚えがあります。しかし、この経験こそが「見るということ、読むということへの執着と歓び」を教えてくれ、今につながっているのだと思います。
さらに「見える」という歓びを格段に向上させてくれたものにルーペと単眼鏡という存在があります。これらを正しく・効率的に使いこなすトレーニングを積めたことが、黒板の板書だらけの普通校での授業に対応できたことにつながったと思います。最近はタブレット端末のカメラ機能で代替する方法も広まってきていますが、即時性(電源を入れてからの時間)、携帯性(単眼鏡はポケットに入る)、普遍性(機器故障への対応)を考慮し、従来からの視覚補助具の活用も習熟しておくべきだと考えます。見る、見えるという歓びは、知りたい・分かりたいという情報探求欲を満たすことなのだと思います。保有視力をフルに活用できる術は、まだまだ多く存在するはずです。見るということに正しく“こだわり“ をもち、日々を豊かにしていきましょう。

6月22日(水)に進路講話を行いました。講師は本校卒業生で開業をされている全盲の方です。開業し、事業が軌道に乗るまでの苦楽の道のり、開業するにあたっての経費や営業方法など視覚障害者で開業している方ならではの具体的方策を聞くことができました。生徒も実際に開業している先生の話に引き込まれている様子で、活発な意見交換がみられました。全ての職種に共通する事項ではありますが、人として何を成し遂げたいのかを明確にもつことが仕事を成功させる原動力であると講話を聴く中で感じました。
今年度は、通常通り臨床実習を開始しています。生徒は、多くの患者様と接する中で臨床経験を積み重ねています。卒業生や地域の方々に支えられ、日々の教育活動を行っておりますので、これからも温かい御支援をお願いいたします。 文責:伊藤
7月4日(月)に運営委員会主催の交流会を行いました。感染対策をしながら体育館で実施し、寄宿舎生が一同に会して楽しいひと時を過ごすことができました。
運営委員会では「交流」「みんなのことを知り合う」「仲良くなる」をキーワードに、5月から話し合いを重ねてきました。当日は3チームに分かれて「ゴロゴロストーン」「シェイクシェイクGOGO」「クイズ」で得点を競いました。ゲームは友達のことを知ることができるよう工夫されており、会が進むごとに「そうだったんだ!」「知らなかった~」と声が上がっていました。日頃一緒に泊まっていない友達と協力したり、意見を出し合ったり、交流会を通してお互いを意識し合うことができていました。
コロナ禍で制限のある生活は続いていますが、今回の交流会は、できることに意識を向け、どうすれば実現できるかを運営委員会中心に考えてきた1つの成果だと感じております。今後も舎生が主体的に取り組み、楽しめる生活作りをすすめていきます。 文責:宇山
今回は専攻科部門について紹介します。専攻科(職業科)であれば、鍼灸マッサージ師になるのだから、進路は決まっているだろうと思われる方が多いと思います。確かに職業的自立に向けて、資格取得するという目標を定めて入学をされているのですが、どの専門分野で資格を活用していくのかを決めて入学されている方は少ないです。
専攻科の進路先は、治療院開業からヘルスキーパーなど多業種にわたり、それぞれに専門性が異なります。どの分野に向けて進路の舵を切り進んで行くのかを、3年間の在学期間の中で決定していかねばなりません。生徒の皆さんが主体的に進路について判断していけるよう、担任と共にサポートを行っている部門が専攻科進路指導部なのです。主な業務は進路情報提供と進路開拓です。そのため、外部機関との接点としての役割、業態情報のリサーチに日々努めています。関心のあること・疑問点など、担任の先生を通してお寄せください。 文責:田中
お問い合わせは以下の電話番号へ
「入学について」「見え方など」様々なご相談、ご質問は代表電話へ
03(3811)5714
(特別支援教育コーディネーターまたは副校長)
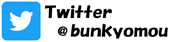
 東京都立文京盲学校
東京都立文京盲学校